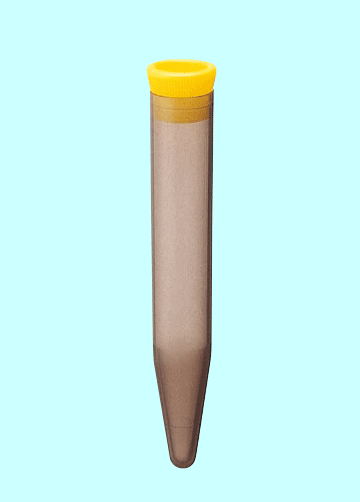WEB総合検査案内 掲載内容は、2026 年 2 月 2 日時点の情報です。
| 項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00637 |
尿中一般物質定性半定量検査 pHpH [urine]1A035-0000-001-911 1A035-0000-001-911 |
|
25 66 |
冷蔵 冷蔵 |
試験紙法 | 5.0~7.5 |
1~2日 |
| 項目 コード |
検査項目 |
|---|---|
00637 |
尿中一般物質定性半定量検査 pHpH [urine]1A035-0000-001-911 1A035-0000-001-911 |
| 採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
|---|---|---|---|
|
25 66 |
冷蔵 冷蔵 |
試験紙法 |
| 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
|---|---|---|
5.0~7.5 |
1~2日 |
備考
容器
参考文献
今井宣子, 他: 機器・試薬 8, 97, 1985.
島田 勇, 他: 機器・試薬 9, 959, 1986.
太子 馨, 松岡 瑛: 検査と技術 18, 1451, 1990.
伊藤機一, 野崎 司: 日本臨牀 57, (増), 45, 1999.
検査項目解説
臨床的意義
健常者では中性~弱酸性を示す。代謝性・呼吸性アシドーシスで酸性、アルカローシスや細菌の繁殖でアルカリ性となる。
健常者の尿は、弱酸性を示すことが多く、pH4.5~8.0の間を変動する。
一般に酸度の高い尿は、色が濃く、低い尿は、色が淡い。尿のpHは、体液の酸度調節を反映して各種疾患で変動し、アシドーシス、アルカローシスにおける病態診断に用いられる。また、動物性食品を摂取したときは酸性となり、植物性食品を多食したときは、アルカリ性に傾く。
熱性疾患、運動後、激しい発汗、飢餓時、代謝性・呼吸性アシドーシスを起こしたときなどは、尿の酸性度が高く、尿細管性アシドーシスでは中性またはアルカリ性、食後消化が旺盛なときは胃内に多量の塩酸が分泌されるため、アルカリ性に傾く。
重曹・有機酸塩などの摂取は尿をアルカリ性にし、塩化アンモニウム・塩化カルシウム・希塩酸などの摂取は、尿を酸性に変化させる。
代謝性・呼吸性アルカローシスでは、中性~アルカリ性となる。尿中に膿汁・血液などが多量に混じるときは、アルカリ性を呈し、細菌尿でも、尿素の分解により炭酸アンモニウムを形成してアルカリ性となる。
【酸性を示す疾患】
糖尿病,高尿酸血症,アシドーシス,痛風
【アルカリ性を示す疾患】
アルカローシス,膀胱炎
関連疾患
E14.91:糖尿病 → E10-E14:糖尿病
E79.0.2:高尿酸血症 → E70-E90:代謝疾患
E87.2.1:アシドーシス → E70-E90:代謝疾患
M10.0.11:痛風 → M05-M14:炎症性多発性関節疾患
E87.3.3:アルカローシス → E70-E90:代謝疾患
N30.9.3:膀胱炎 → N30-N39:その他の尿路系疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.